社会心理学から「心の力学」を学ぶ

今回は、社会心理学の本を読んで、人の「心の動き」について考えてみたいと思います。
原理
ヒトの「心の動き」については、西田公昭(著)『なぜ、人は操られ支配されるのか』(さくら舎, 2019)に分かり易く書かれています。
本記事では、この本を参考にしています。
本記事では、人の「心の動き」について考える上で、本質的であると思われることを、その本を参考にして、述べて行きます。
つまりは、心の動きの「原理」になり得ることを述べて行きたいと思います。
不確実性に関するバランス
ヒトの心(脳)は「不確実なこと」に対して敏感で、頭の中に生じている不確実性と言うもののバランスを取るかのように行動してしまうようです。
つまり、ヒトは、
不確実性(不安・悩み・迷い)が高まると、確実性の高いものを求める様になり、逆に、
確実性(安心・安全・確信)が高まると、確実性の低いものを求める様になるようです。
(なお、このことは、前回の記事でも紹介させて頂きました。)
実際に、その本によると、不安定な状況に耐えられない時、人は(政治や組織などにおいて)絶対的な支配を求めることがあるそうです。
絶対的な基準はない
あらゆる物事や現象には、絶対的な物の見方の基準はないそうです。
つまり、あらゆる物事や現象は、視点を変えれば、どのようにでも解釈できる(意味付けできる)と言うことだと思います。
(なお、このことは、以前の記事でも紹介させて頂きました。)
その本によると、正常と異常、善と悪の間には、実は絶対的な基準はないそうです。
絶対的な基準がないので、人の心は、時に、その間で揺れ動くそうです。
ただ、その本によると、善悪の判断基準は、所属する社会(周囲の環境)における暗黙の価値観に左右されるものであるそうです。
つまり、所属する社会や時代が変わると、善悪の判断基準も変わると言うことのようです。

分類と世界分節
その本によると、人間には、分類したがったり、まとめたがったりする傾向が本能的に備わっているそうです。
例えば、血液型で、ヒトの性格を分類するのは、その傾向の現れであるそうです。
血液型分類を使うと、相手との付き合い方を考える上でのヒントや手掛かりになり、何もないまっさらな状態から手探りでアプローチするより楽で安心できるそうです。
哲学には、「世界分節」という言葉があります。
世界分節とは、世界を意味のまとまりとして区切ることを意味します。
さらに「言語が世界を分節する」という言葉もあります。
これは、つまり、何の手掛かりもない世界(=全体的でぼんやりした世界)を言葉によって区切ることで、世界の物事をハッキリと認識することを意味します。
例えば、「雲」という言葉を知らなれば、空は青い背景に時折白いものが混じったぼんやりした全体として認識されることになると思います。
つまり、空の「白いもの」を「雲」と名付けることで、人間は空を「青い背景」と「雲」に分節しています。
血液型分類も、言語による世界分節の一つなのだと思います。
その本によると、良く知らない相手を血液型で大まかに分類して、仮にでも枠組みにはめてしまえば、対応の仕方も分かり、楽になれると言う心理が人間には働くそうです。
そして、実体験が、その人の中で、分類の信憑性(しんぴょうせい)を高めることになるそうです。

内集団と外集団
その本によると、人間は内と外に分けたがる生き物であるそうです。
つまり、生き抜くために、敵と味方に分けて来た名残りの様なものが、ヒトには本能的に備わっているようです。
自分が属している集団は、内集団と呼ばれるそうです。一方で、
自分が属していない集団は、外集団と呼ばれるそうです。
そして、自分の集団、つまり内集団を好意的に見るようになり、外集団には否定的になるそうです。
ただ、内集団と外集団の線引きの基準は、絶対的なものではないそうです。
その基準(境界線)はあくまでも、自分とメンバーの正義(判断)でしかないそうです。
ちなみに、地球上の生命には、外界と内界(自己)の間に仕切り(=膜)が必ずありますが、外と内を仕切ることは、生命にとって何か本質的なことなのでしょうか。
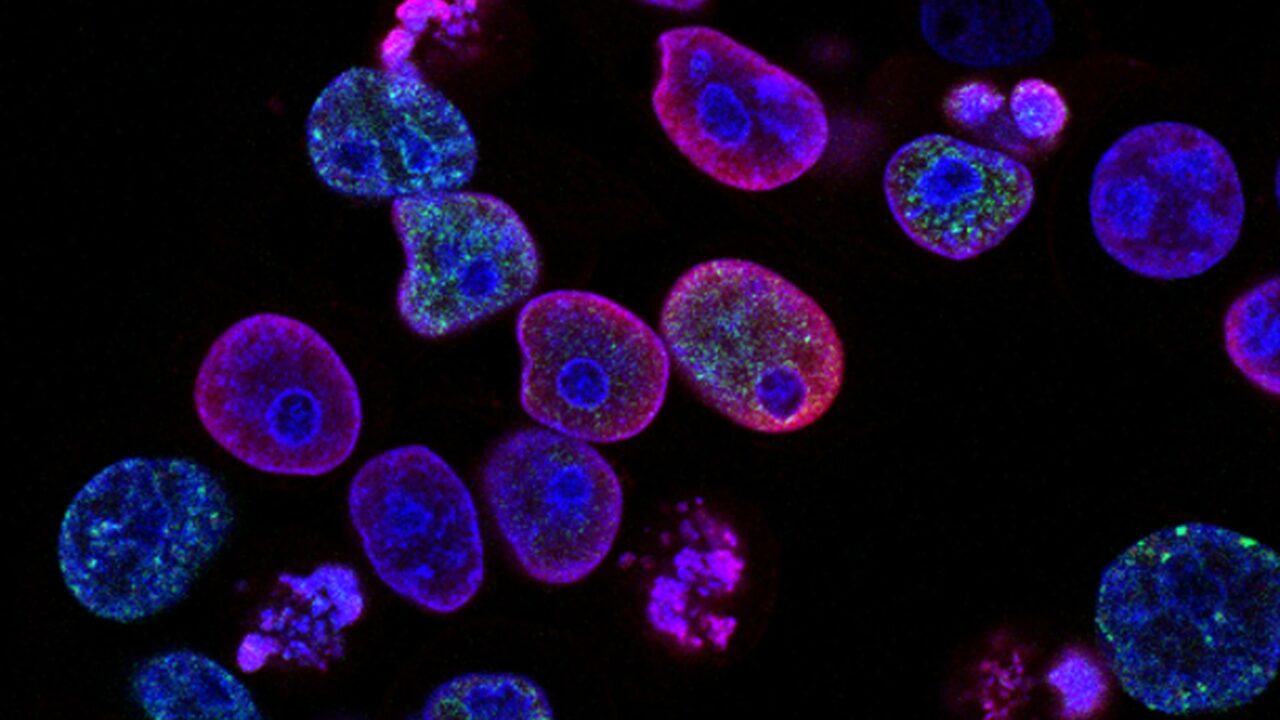
集団を作る理由
その本によると、ヒトが集団を作る理由は、安心できて、自分が楽になりたいからであるそうです。
言い換えれば、集団を作りたがる傾向の根本的な理由は、生物学的にできるだけエネルギーを使いたくないからと言えるそうです。
つまりは、一人で重荷を背負いたくはなく、少しでも楽をしたいと言う心理が背景(無意識)にあるようです。
所属する集団があることで、ヒトは安心感が得られるそうです。
さらに、価値観を共有する人達が集まることによって、力が生まれるそうです(集団の力)。
つまり、一人ではできない事が、集団では可能となり、強くなれるのだそうです。
何かを達成したいのであれば、一人で頑張るより、集団で取り組んだ方が目標を達成し易くなるそうです。
集団が力を持ち、多数派になれば、世の中を動かすことも可能になるそうです。
また、自分が属する集団が収(おさ)めた成功を自分の手柄のように感じることがあるそうです。
確かに、日本人がオリンピックで金メダルを取ったり、ノーベル賞を取ったりすると、何だか誇(ほこ)らしい気分になります。
なお、集団の形成とは、新たなシステムの形成であり、新たな上位の階層構造が形成されたことになるのかもしれません。つまりは、新たな生命体の形成とも言えるのかもしれません。

集団の維持と団結
集団を維持したり団結させる方法には、色々な方法があると思いますが、その本によると、次のような方法があるそうです:
自分達の集団を高等、優れているとする一方で、敵とみなす集団は意味がない、価値がないと貶(おとし)め、差別する。
つまり、外に敵を作ると、集団を維持したり、団結を強くしたりすることが可能になるそうです。
残念ながら、人間には、差別すると安心する、差別する方が心地良いと感じる心理があるそうです。
このやり方は、物理学的に言えば、集団内を秩序立てるには、外に無秩序なものを発散する必要があると言うことになるのかもしれません。
熱力学的な言い方をすれば、集団内のエントロピーを減少させるには、集団の外により大きなエントロピーの増大を吐き出す必要があり、内外のトータルとしてエントロピーの増大を実現しなければならないと言うことになるのかもしれません。
エントロピーとは、物事の乱(みだ)れ具合を表す量です。つまり、対象の「乱雑さ」を表す量です。
詰まる所、外にエネルギーのはけ口があることで、内集団が維持され・団結を強くする、と言うことのようです。
この仕組みは、生物学などで出て来る「散逸構造」とも関係があるのかもしれません。
散逸構造とは、エネルギーや物の流れを持つにもかかわらず、形を一定に保つ構造のことです。
なお、生命は、散逸構造を取っていると考えられています。台風や竜巻も散逸構造ですが。
すると、やはり、内集団には、エネルギーの注入も必要、つまり、何らかの成果や報酬または旨(うま)みも必要と言うことになるのだと思います。

集団の境界線
その本によると、内集団と外集団の境界線は流動的で、状況によってその都度、都合よく変化するそうです。
また、集団内の力学はダイナミックで制御がとても難しいそうです。
つまり、集団内の力関係は突然変化するそうです。
ちなみに、台風や竜巻は「散逸構造」を取っていると考えられていますが、生命とは異なり、これらには「仕切り」や「膜」つまり「境界線」がありません。
ゆえに、一時的に発生しますが、しばらくすると、自然に消滅します。
つまり、明確な「境界線」がないものは、非常に不安定であると予想されます。
ゆえに、内集団と外集団の境界線についても、境界線があいまいなものは、非常に不安定で自然消滅する可能性もあるのかもしれません。
ただ、発生源がある限り、自然発生する可能性もあるのだと思います。

二項対立の解決法
その本によると、対立や争いの発端は、基本的には、人間の線引きしたがる性質にあるそうです。
人間には、線引きをして、内(味方)と外(敵)に分けたがる本能がありますが、分け過ぎると「分断」「対立」「不寛容」に繋(つな)がるそうです。
内集団と外集団が本格的に対立してしてまった場合、解決策としては、第三の集団を作ると上手く解決できることがあるそうです。
物理学的に言うと、二体問題を三体問題にすると言うことでしょうか。
二体問題は、解析的に解ける問題なので、内集団と外集団のどちらかに勝敗がついてしまいます。つまり、力が強い方が勝つことになるのだと思います。
しかし、三体問題は、解析的に解けない問題なので、勝敗がつくことはなく、3つの集団とも生き残れるのかもしれません。

「信じる心」の仕組み
その本によると、人が意思決定をする時は、「外界からの情報」と「内界にある情報」が組み合わせられているそうです。
「外界からの情報」とは、視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚によって得られる情報です。
「内界にある情報」とは、頭の中に記憶されている知識や信念です。
また、「内界にある情報」は、「ビリーフ」とも呼ばれるそうです。
「ビリーフ」とは、自分が正しいと信じている事です。
「ビリーフ」は、次の3つのどれかによって形成されるそうです。
- 自分の経験によって
- 推論によって
- 他者(権威者など)との相互作用によって
結局のところ、信じるか信じないかの大きな根拠になっているのは、自分の所属している集団の正義(判断基準)であるそうです。
そして、「ビリーフ」は、主観的なもので、権威や集団文化の影響を強く受けてしまうそうです。
「外界からの情報」や「ビリーフ」を操れば、人の思考(信じる心)は支配されてしまうそうです。
例えば、その本によると、人は客観的な情報源を詐欺師に奪われてしまうと、一人では適切な判断を下せなくなることもあるようです。ゆえに、詐欺師は家族や社会からその人を引き離そうとするそうです。
外界あっての内界
その本によると、人が何かを決めて行動するにあたっては、内界つまり本来の素質(個人の趣味や嗜好(しこう)、クセ、欲求、能力、性格など)以外の要素が大きく働くそうです。
つまり、外界(他者や社会)から、「見えない力」で、ある行動を取るように仕向けられているそうです。
哲学的にも(構造主義)、内界と外界の相互作用が、人生において非常に重要であるようです。
生まれたばかりの内界には、外界の情報は何も入っていないので、取り敢えず、外界から色々なことを学びます。
すると、無意識の内に、外界に強く依存した思考や身体になりますが、一方で、
内界にある「生まれながらの自分の気質」が次第に分かるようになるようです。
外界との相互作用によって、内界にある自分の気質に気が付いたならば、自分の気質を発揮できる外界で、自分の気質を発現させれば人生を享受(きょうじゅ:味わい楽しむ事)できるようです。
内界の気質は、無意識とも関係している様なので、恐らくは、なかなか変えられないものだと思いますが、外界は常に良い方向にも悪い方向にも変化するものなのだと思います。

返報性のルール
人間には、相手に何かしてもらったら、そのお返しをしないといけない、と感じる心理があるそうです。
つまり、人間には、本能的に貰(もら)い過ぎてはいけないと言う「心の動き」があるようです。
そして、様々な意味において(お金や才能などで)、貰い過ぎていると感じると、自然に誰かのために返す行動に出るようです。
アメリカでは、大金持ちになると、慈善活動や寄付を始めるようですが、これも「返報性のルール」に因(よ)るものなのだと思います。
「返報性のルール」の背景には、貰い過ぎを続けていると、最終的には「身を滅ぼす」または「存続できなくなる」と言う心理があるのかもしれません。
もしくは、「貰い過ぎている」という状態は、エントロピーが減少している状態であるので、つまり一箇所に物(お金)が集まっている状態なので、一箇所に集まってしまった物(お金)を、自然の摂理に従って拡散させないといけないのかもしれません、つまりエントロピーを増大させる必要があるのかもしれません。
思い込み
偽薬効果
その本によると、効き目があると信じてニセ薬を飲むと、暗示の力(権威の力)が働いて、実際に効果が出ることが少なくないそうです。
期待や思い込みがあると、その効果のように思えるものが日常生活の中でことさら目に付くようになるそうです。
目に付くようになるのは、「認識することで、その存在が確定する」という量子力学の考え方に関係しているのかもしれません。
認証バイアス
その本によると、(限定された・個人的な)体験によって、ある事を思い込んでしまったら、その誤りを正すことは難しいそうです。
人は一度思い込むと、後から「おかしい事」や「つじつまの合わない事」が出て来ても、なかなか考えを変えられないそうです。
むしろ、自分の思い込み、そして思い込みの結果として取った行動に合致する、都合のよい情報ばかりに目が行って、「おかしな点」や「つじつまの合わない点」には気が付きにくくなるそうです。
例えば、占いなどがその例であるようです。

おまけ:従う事と創造性
その本によると、権威者や権力者に従うことに慣れてしまうと、自分で考えなくなってしまうそうです。
権力者からすれば、配下の者達には、自分で物を考えて欲しくないのだと思います。
自分で考えられると、何かと面倒だからだと思います(物事(悪事?)がスムーズに進まなくなるから)。
つまりは、素直に従う人を高く評価することになるのだと思います。
この権力者の評価法は、時代背景や状況によって、良い方向にも、悪い方向にも働くようです。
その本によると、日本の教育には、未だに軍国主義的な全体主義思想による教育が一部残っているそうです。体育の授業の一部がその良い例であるようです。
ちなみに、陰陽五行的には、先生や権力者の言う事に素直に従っていない人の方が、「表現する力」や「何かを自分で生み出す力」が強いと考えれるようです。







