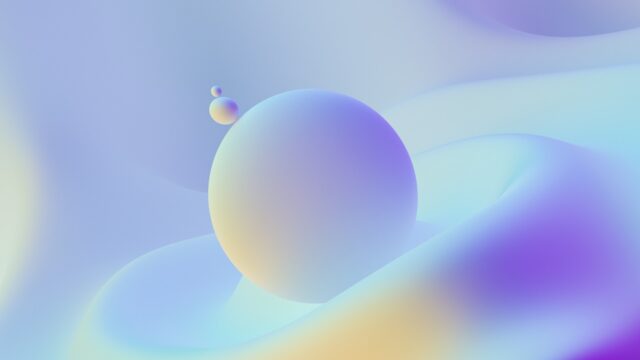心理学から「人に関する有益なこと」を学ぶ

今回は、心理学の本を読んで、「人の性質」や「その中に隠された本質」について考えてみたいと思います。
世界の認識
心理学に基づいた「人の性格に関する事柄」についての話は、ブライアン・R・リトル(著)『自分の価値を最大にするハーバードの心理学講義』(大和書房, 2016)に分かり易く書かれています。
本記事は、この本を参考にしています。
その本によると、
「私達は、他者を理解しようとする試みを通じて、自分を深く理解することになり、自分を深く理解することによって、世界を違った視点で捉えられるようになり、もっと自分の能力を活かすことができるようになる」
そうです。
さらに、「個人的構成概念理論」という心理学の学説によれば、
「人にはそれぞれ独自の評価基準があり、それによって物事を予想したり、自分や他者を解釈したりしている」
そうです。
ここで、評価基準とは、個人の欲望や関心のようなもののことで、例えば、
- 「お金持ちか←―→貧しいか」
- 「頭が良いか←―→良くないか」
- 「美しいか←―→美しくないか」
- 「人当たりが良いか←―→悪いか」
- 「面白いか←―→つまらないか」
- 「スポーツが得意か←―→苦手か」
- 「医者や弁護士か←―→医者や弁護士でないか」
などが評価基準になるそうです。
この評価基準は、私達が周囲の世界を理解するための便利な「枠組み」(判断基準?)にもなれば、私達を閉じ込める檻にもなるそうです。
言い換えれば、その枠組みは複雑な世の中を迷わずに歩くための道標にもなる一方で、自分や他者を凝り固まった考え方で捉えてしまう罠にもなるそうです。
人は、他者を解釈する枠組み(判断基準)が多くなるほど世の中に適応しやすくなり、逆に枠組み(判断基準)が少ないと、変化して行く状況に上手く対処できず、トラブルを乗り越えることが困難になってしまうそうです。
自分が他者をどのように判断しているかは、世界を理解する枠組み(判断基準)にもなれば、自分自身を拘束する足枷(あしかせ)にもなるそうです。
枠組み(判断基準)に囚(とら)われてしまえば、人生を思い通りに歩めなくなってしまうそうです。
私達は、個人的な評価基準で世界を自分なりに解釈し、他者の性格や行動を予測しているそうです。
また、この評価基準に基づいて、人は他者を分類しているそうです。
例えば、「敵なのか」それとも「味方や仲間なのか」と言った分類です。
私達は他者を客観的に解釈していると思っていますが、実は、その評価基準となっている物差しは、個人の感情や経験の影響を強く受けており、それぞれ独自に形作られているそうです。
同じ出来事でも、捉え方が柔軟な方が上手く対処できるそうです。
評価基準のレパートリーが少ない人は、世界を解釈する自由度が低くなるために、日常生活で日々新たに生じる出来事に上手く対処できず、不安を感じ易くなるそうです。
さらに、個人の評価基準は、単体で作用しているのではなく、相互に作用するいくつもの評価基準と伴に、人の価値観を作り上げているそうです。
その他の基準との結び付きが強いものが、個人の最も大切にしている「価値観の核」になっているそうです。
単一の評価基準だけではなく、他の評価基準も尊重し、それを自らの価値観の体系に取り入れることが大切であるそうです。
例えば、「弁護士か←―→弁護士でないか」という評価基準が唯一の基準になってしまうと、司法試験に落ちてしまった場合、大きなショックを受けてしまいますが、行政書士や司法書士または企業の法務部という評価基準があれば、前進することができるかもしれません。
ただ、その本によると、価値観の複雑なネットワークの中心にある、核となっている評価基準に何らかの異変が生じると、大きな感情的反応を伴う、強い抵抗感が生じることがあるそうです。
また、特定の評価基準に執着すると、視野が狭くなったり、不安になったり、攻撃的になったりすることもあるそうです。
しかし、柱となる評価基準が複数あれば、一つが上手く機能しなくても、別の評価基準で世界を解釈することができるそうです。
また、一つの評価基準で、自分や他者を捉(とら)えるべきではないそうです。
世界を自由に解釈できるようになることで、人生の満足度も高まるそうです。
余談
宇宙がビックバンを起こす前に、空間を急膨張(インフレーション)させたように、人が生きて行く上でも、認識の拡張、つまりは評価基準の拡張が必要なのかもしれません。
また、この認識のインフレーションのことを「教養」と言うのかもしません。
ちなみに、哲学の世界でも、人は世界を自分の「欲望」や「関心」に応じて認識している、と言われています。
そして、その「欲望」や「関心」は、世界に「意味」や「価値」を与えるそうです。
さらに、釈迦(しゃか)の思想にも、できる限り正しく世界が見えるように自分を作り上げて行くことが、生きる目的になると言うのがあるようです。

自然はバランスを取りたがる
その本によると、人間の様々な性格特性(外向性、協調性、開放性など)は、私達の祖先が30人程度の集団で狩猟採集生活を送っていた時代に形成されたそうです。
そして、性格特性(パーソナリティ特性)は、遺伝的な影響もあり、長期的にはあまり変化しないそうです。
刺激に対するバランス
外向的な人は、脳の特定領域における覚醒レベルが、普段は低い状態にあるそうです。
内向的な人は、脳の特定領域における覚醒レベルが、普段は高い状態にあるそうです。
そして、日常生活で適切に振る舞うには、覚醒レベルを適切に保つ必要があるそうです。
ゆえに、外向的な人は、覚醒レベルを上げようとし、
一方で、内向的な人は、覚醒レベルを下げようとするそうです。
普段から覚醒レベルが高い内向的な人は、適切なレベルを維持するために、刺激的な状況を避けようとするそうです。
内向的な人は、刺激の多い状況ではパフォーマンスが落ちることを理解しているそうで、人付き合いが悪くなる傾向があるそうです。
逆に、普段から覚醒レベルが低い外向的な人は、刺激的な状況を好み、熱い議論が交わされるような環境にいる時こそ、自分のパフォーマンスが上がることを知っているそうです。
なお、アルコールは、その覚醒レベルを下げる効果が、
コーヒーは、その覚醒レベルを上げる効果があるそうです。

性格と環境のバランス
その本によると、遺伝的な性格特性と環境が一致すると成功し易いそうです。
しかし、人生ではいつも普段通りの自分で居られる訳ではないそうです。
その時に力を発揮するのが自由特性と呼ばれる「変化できる性格」だそうです。
「変化できる性格」は、プロ意識や愛情によって生み出される後天的な性格であるそうです。
ただ、長期間に渡って本来の自分と違うキャラクターを装うと、心身に負荷がかかることがあるそうです。
また、私達の生活の質は、環境に大きく左右されるそうです。
生まれ持った性格特性が環境に合っていれば、幸福度も高まるそうです。
例えば、社交的な人は社交性が求められる仕事や課題に従事している場合において、強く幸福を感じることが研究で分かっているそうです。
このように、遺伝的な気質と社会的な環境が一致すると、より良い結果に繋(つな)がるそうです。
逆に、ミスマッチがあると、リスクが生じるそうです。
研究によれば、日常的に生まれつきの性格を抑えた行動をとっていると、自律神経が覚醒した緊張状態に陥り、慢性化すると健康に悪影響を生じやすくなることが分かっているそうです。
しかし、問題を誰かに告白すると、自律神経の覚醒レベルが下がって安定することも分かっているそうです。
問題を告白すると、最初は覚醒レベルの上昇が見られるそうです。
それまで秘密にしていたことを誰かに伝えるのは、簡単ではないからだそうです。
しかし、その後は覚醒レベルが低下し、告白前よりも低いレベルで安定するそうです。
つまり、告白した人は、免疫システムの向上などの理由によって、以前よりも健康になるそうです。
また、本来の自分を抑制しようとすることで、かえって本来の自分が漏れて出てしまう場合があるそうです。
そのような場合は、「回復のための場所」、つまり、普段と違う行動がもたらすストレスから逃れ、「本来の自分」としてありのままに過ごせる休憩所を作ると良いそうです。
都市でのバランス
その本によると、都市は過負荷な刺激を生み出す装置であると捉えることもできるそうです。
そして、人は、その刺激を減らすために、「他者に介入しない」などの適応戦略を採用し、都市ではそれが当然の規範と考えることで、過負荷な刺激の問題に対処しようとしているそうです。

創造的な人は量子計算的な思考
クリエイティビティ(創造性)の定義
創造性を定義することは、なかなか困難なことであるそうですが、カルフォルニア大学付属の研究所は、クリエィティブな建築家の定義(基準)として次の3つを定めたそうです。
- 斬新かつ革新的な建築物を設計した来たこと
- それらを発想だけではなく実際に行動に移したこと
- これらの作品によって建築分野の新しい基準を打ち立てたこと
この定義は次のように一般化できるかもしれません。
- 斬新かつ革新的な創作物を生み出したこと
- それらを発想だけではなく実際に行動に移したこと
- これらの創作物によってその分野の新しい基準を打ち立てたこと
なお、創造性は、革新的で慣習に囚われないアイディアを、困難な問題の解決策に変えることと関連しているそうです。
クリエィティブな人の共通点
その本によると、創造的な人の子供時代は、個人の自主性や自律性が尊重され、自分の好きなことをさせてもらえていた場合が多いそうです。
また、創造的な人は、規則や慣習に従う活動を嫌い、自らの衝動やアイディアを抑え込むものに抵抗するそうです。
また、創造的な人は、細部へのこだわりがあり、柔軟な思考や洗練された言語表現、知的好奇心に優れているそうです。
また、創造的な人は、出来事を見て直ぐに結論を導こうとせずに、その意味や意義を自由に解釈するそうです。
この傾向は、結論を急がずにオープンな態度で物事に関わることに繋(つな)がりますが、秩序を欠くことにも繋がるそうです。
また、創造的な人は、出来事や物事に潜む意味や可能性を理解しようとする傾向があり、目に見える事実以上の可能性を想像するそうです。
また、創造的な人は、プロジェクトの序盤で複雑さ(混沌)を好み(自由で多様なアプローチを好み)、プロジェクトが進むにつれ、「解決すること」に強く焦点を当てるそうです。
また、創造的な人は、長い時間をかけて複雑な問題に取り組みますが、最後には型にはまらないシンプルかつエレガントな方法で問題を解決しようとするそうです。
また、創造的な人は、自分を説明する言葉として「独創的」「個人主義」「熱心」「勤勉」などの言葉を選んだそうです。
一方で、創造性の低い人は、「責任感がある」「誠実」「信頼できる」「思考が明快」「寛容」「思いやりがある」などの言葉を選んだそうです。
また、創造的な人は、内向的な傾向があり、人間関係に積極的ではなく、他者と深く関わろうとしない傾向があるそうですが、他者と強く対立することもないそうです。
また、創造的な人は、その情熱を自らの創造的なプロジェクトの追求に向けており、気まぐれであるためか社交性を持続させるのは得意ではないそうです。
ただ、創造的な人は、「対人的な落ち着き」や「魅力的で愛情深い振る舞いをする能力」は持っているそうですが、あまり表には出ないようです。
また、創造的な人は、ある研究報告によると、以下の特徴も持つそうです。
- 知的(高校の成績は平凡だが特定の科目では優秀)
- 率直
- 頭の回転が速い(一般的にはIQは120程度で超高IQという訳ではない)
- 要求が厳しい
- 攻撃的
- 自己中心的
- 説得力がある
- 弁が立つ
- 自信がある
- 物怖じしない
- 悩みや不満を包み隠さずに表現する
また、創造的な人は、個人主義を重んじ、他者に特に好印象を与えようともしないので、組織内で様々な軋轢(あつれき)を生じさせる可能性があるそうです。
また、創造的な人は、魅力やカリスマ性がある一方で、血の気が多く、同僚に必死に懇願されても自らを抑えることができない場合もあるそうです。
また、創造的な人は、自分の事で頭がいっぱいで、短気で、細やかな仕事を軽視し、協力的かつ合議的な作業環境を築くためのコミュニケーションに関心が薄いと言った傾向があるそうです。
つまりは、組織向きではないそうです。
また、創造的な人の成功には、「周りの人々のサポート」や「様々な人々の協力」が不可欠であるそうです。
また、創造的な人は、自我強度のスコアが高く、「知的」「機知に富む(臨機応変?)」「現実的」「対立に強い」などの特徴をもつそうです。
また、創造的な人は、身の回りで生じる不要な情報を除外するための「フィルタリング能力」が低いそうです。
また、創造的な人は、フィルタリング能力が高い人なら排除してしまうような様々なアイディアやイメージを、アイディアの源として保持し続けられるそうです。
そのために、創造的な洞察力や鋭敏な感受性、斬新な視点などが得られるそうです。
また、知性が高ければ、フィルターをくぐり抜けて入って来る情報の洪水に対応し易くなるそうです。
また、創造的な人は、挑戦的で、神経質な性格である場合が多いそうです。
そして、時には奇妙な振る舞いをすることもあるそうです。
また、創造的な人は、経験に対してオープンであるため、対立する考えを同時に持つことができるなど、複雑な思考ができるそうです。
余談
創造的な人の思考は、何となく量子コンピュータ的な思考だと思いました。
古典コンピュータは、0か1かのどちらかの値で情報を表します。
一方で、量子コンピュータ(量子力学の原理を利用するコンピュータ)は、0と1の重ね合わせで情報を表現します。
つまり、量子コンピュータは0と1という対立する状態(情報)を同時に持つことができます。
そのため、量子コンピュータは同時に多数の状態を表現でき、量子回路(ユニタリ変換)を巧みに用いることで超高速な計算が可能となります。
ただ、量子コンピュータは、あらゆる計算(問題)に対して、超高速な計算ができると言う訳ではありません。
(現在のところ、古典コンピュータより劣る場合の方が多いと考えられています。)
例えば、量子コンピュータは「膨大な組み合わせの中から適切なものを確率的に選び出す」と言うような特定の問題に向いていると考えられています。
このような量子コンピュータの特徴は、創造的な人の次の特徴に部分的に似ているような気がしました。
- 「対立する考えを同時に持つことができる」
- 「複雑な問題に取り組み、最終的にはシンプルかつエレガントな方法で問題を解決しようとする」
- 「高校の成績は平凡だが特定の科目では優秀」(特化型で汎用的ではない)
さらに、創造的な人には、身の回りで生じる不要な情報を除外するための「フィルタリング能力」が低いという特徴がありましたが、
量子コンピュータも、入力時や計算中のノイズ(量子状態の乱れ)に弱く、ノイズを取り除く機能が付いた量子コンピュータの開発・完成が現在待望されています。