生物学からシステムの本質を学ぶ
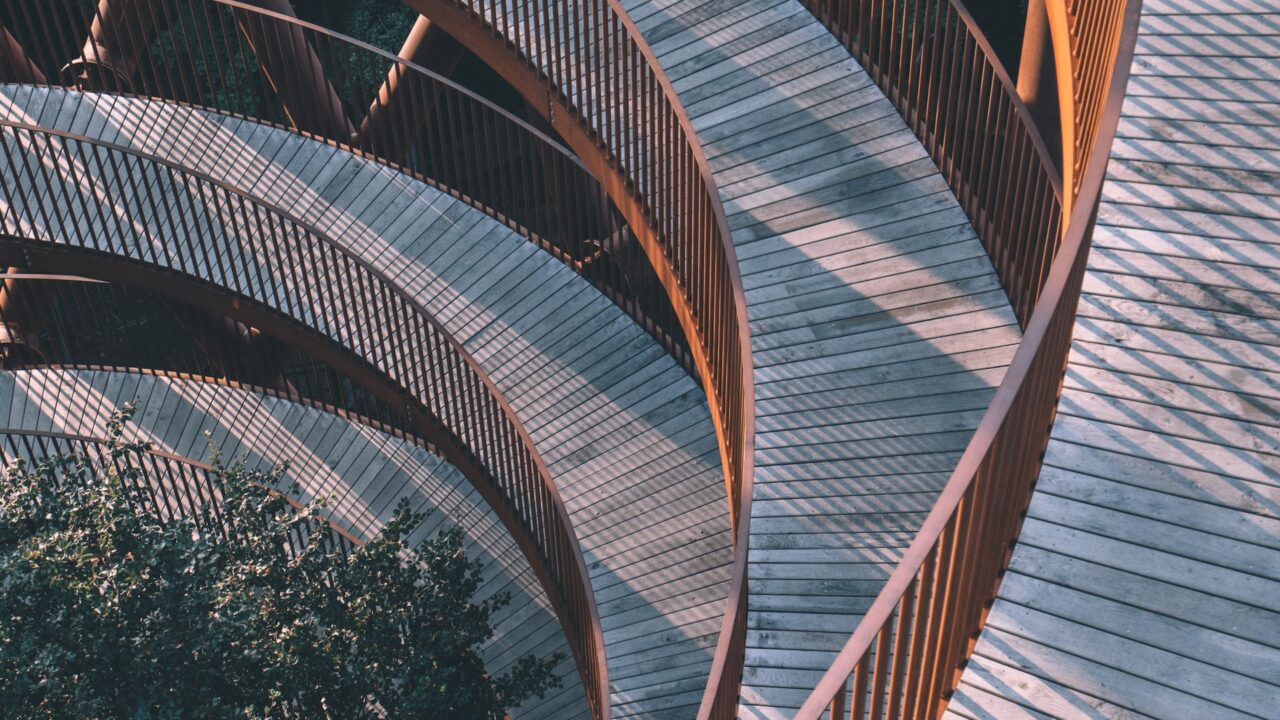
今回は、生物学の本を読んで、システム(企業や組織)の本質を探究してみたいと思います。
生物の定義に従えば
生物学に関することは、更科功(著)『若い読者に贈る美しい生物学講義 感動する生命のはなし』(ダイヤモンド社,2019)に分かり易く書かれています。
本記事では、この本を参考にしています。
その本によると、地球上の生物は、次のように定義されるそうです。
- 外界と自己(=内界)の間には仕切り(=膜)がある。
- 外界との間で物質やエネルギーの出入りがあり、内界には物質やエネルギーの流れや変換(=代謝)がある。
- 自己を複製する。
つまり、この3つの条件を満たすものは生物であることになります。
一方で、その本によると、レオナルド・ダ・ヴィンチは地球を生物と考えていたようです。
つまり、地球と生物には類似性(似ている部分)があると言うことのようです。
それでは、宇宙は生物でしょうか。
宇宙は、代謝のようなものはあるのかもしれませんが、膜(宇宙の果て?)はないような気がします。また、複製もしていないと思います。
ゆえに、宇宙は生物ではないと思います。
それでは、国や国家は生物でしょうか。
確かに、国には、国境があります。そして、他国との間に物質の出入りがあり、自国には物質の流れや物質の加工(変換)があります。
ただ、自国の複製はしていないと思います。戦争をして他国を自国の一部にすることが複製であると考えられなくもないような気はしますが。
従って、国は、膜と代謝は満たしますが、複製はしていないので、生物ではないと言うことになると思います。
一方で、都市は複製している感じなので、生物なのかもしれません。
しかし、都市は、生物である人間がいないと複製や代謝をしないので、正しくは生物ではないと思います。
ただ、今回は、人間に視点を当てるのではなく、都市のようなものを生物かの様に見る視点に立ってみたいと思います。
それでは、会社や組織は生物でしょうか。
確かに、会社には仕切りがあり(社内と社外の区別が一応あり)、さらに会社には物質や人の流れもあり、物質や情報を別の物に変換していると思います。
また、会社は、会社を大きくして支店などを増やすこともあるので、複製していると考えられます。
従って、会社や組織は生物かの様に見ることができるかもしれません。
なお、正確には、会社や組織は、人間がいないと代謝や複製をしないので、生物ではないです。
それでは、家庭(=家)は生物でしょうか。
家庭(=家)には仕切りがあり(=家内と家外の区別があり)、さらに家庭には物質や人の流れもあり、物質や情報を別の物に変換していると思います。
また、家庭は、親から子へ引き継がれたり、子供たちが新たな家庭を作ったりしているので、複製していると考えられます。
従って、家庭(=家)は生物かの様に見ることができるかもしれません。
なお、正確には、家庭(=家)は、人間がいないと代謝や複製をしないので、生物ではないです。
まとめ
人間が居ることが前提となりますが、都市、会社、組織、家庭が生物の三条件(膜、代謝、複製)を満たすことが分かりました。
すると、生物学を学ぶことで、会社や組織において、その学びを活かせる・活用できる・応用できることがあるかもしれません。
と言う訳で、この記事では、会社や組織において、生物学の学びが役立ちそうなことを上述の本に基づいて紹介して行きます。
なお、各人を中心として、「人間→家庭→会社→都市」と類似性の高い構造が階層的に広がって行く現象は、とても興味深いと思います。マトリョーシカ人形のようです。

生物学の学び
1)膜の役割
生物、つまりは、細胞に膜(仕切り)がある理由は、膜の中で化学反応を効率的に行うためであるそうです。
なお、全ての生物(動物、植物、細菌)は、細胞からできています。細胞が生物の最小単位になります。
また、細胞内は、化学反応の塊(かたまり)であるそうです。
確かに、会社に膜(仕切り)があるのは、仕事を効率的に行うためなのかもしれません。
工場は工場として町の中で区切られていた方が、安全で効率的と言うことだと思います。

2)代謝と散逸構造
生物の定義によれば、生物の体内では代謝が行われています。
代謝とは、外界から物質(食べ物)を取り込み、その物質つまり有機物を酸素と反応させて、化学エネルギーに変換する一連の過程を指しているようです(動物の場合)。
ここで、化学エネルギーとは、化学反応において、分子の中の結合が切れたり・作られたりすることによって、生じるエネルギーです。
そして、この化学エネルギーは、生物の中で様々な形で利用されますが、最終的には熱エネルギーとなり体内で消費されます、または熱エネルギーとなり体外へ出て行きます。
また、生物の体内で不要となった物質、例えばCO2は、外界に排出されます。
このように、生物の体には、物質やエネルギーの流れ(変化)があります。
なお、常に流れや変化がある状態のことを「非平衡状態」と呼びます。
一方で、グラスの中の水のように、見かけ上は何の変化も起こっていないかのような状態を「平衡状態」と呼びます。
つまり、平衡状態は、流れのようなものがない状態、つまり一方的な偏りがない状態です。
生物は、無生物のように全体の形が殆ど変わらないにもかかわらず、その内部は平衡状態ではなく非平衡状態である、つまり「流れがある」という特徴をもっているそうです。
なお、流れを持つにもかかわらず、形を一定に保つ構造を「散逸構造」と呼びます。
生物以外で散逸構造を持つものとしては、
- 台風
- 海上にできる渦(うず)
- ガスバーナーの炎
などが知られているそうです。
散逸構造を取るものは、エネルギーを吸収し続けないと、形を維持できないそうです。
また、その本によると、生物が代謝を行う理由は、生物が散逸構造をしているためで、散逸構造をしている理由は、たまたま奇跡が起きたからかもしれないと言うことでした。
少しややこしくなりましたので、まとめますと、次のようになります。
生物には、物質やエネルギーの流れがある。つまり、代謝がある。
生物には、常に流れや変化があるので、非平衡状態である。
生物は、非平衡状態なのに形が変わらない。つまり、散逸構造である。
生物だけが、散逸構造なのではなく、台風なども散逸構造である。
会社や組織も、散逸構造であると言えなくもないような気もしますが、やはり生物や台風の散逸構造とは少し違う感じもします。しかし、厳密なことは、この記事ではあまり気にしないことにします。
3)複製と生物の急速な繁栄
その本によると、生物の約40億年にも及ぶ進化の過程には、シンギュラリティ(=特異点)つまり急速に生物が進化するきっかけとなった時点があったそうです。
ずばりその時点とは、生物が二体の複製を作り始めた時であるそうです。
ただ、その二体は、全く同じものではなく、違い(変異)があるそうです。
変異とは、DNAのコピーミスのことのようです。OSのバージョンアップのようなものと考えても良いかもしれません。
さらに、その二体の両方が大人になることは難しく、一方は大人になれないような厳しい環境が前提としてあるようです。
このような場合に、生物には自然選択が働くようになるそうです。
つまり、生物としての性能の良い方が生き残るようになり、生物としての性能が爆発的に向上し始めるようです。
ただ、自然選択には、不利な生物を除く働きしかないそうです。
何だか非常に生々しい話です。まさに企業や組織で起きているような淘汰(とうた)や進化のような気がします。
例えば、MacかWindowsかを選択する時、確かにその選択者に不利だと思われてしまう方が除かれるのかもしれません。
製品がある一定のレベルに達すると、利点よりも不利な点に注意が向かってしまうものなのかもしれません。
すると、多くのお客さんにとって、不利な要素を持たない製品やサービスが人気になることもあるのかもしれません。

4)自然選択が働く条件
上述の通り、生物に自然選択が働く条件は、次のようにまとめられます。
- その種に遺伝する変異(違い)があること。
- 大人になる数より多くの子供を産むこと。
自然選択が働かなければ、つまり、上の2つの条件が揃(そろ)わなければ、生物は存在し続けることはできなかったと考えられるようです。
つまり、生物は常に同種の仲間と「いす取りゲーム」をして来たと言うことかもしれません。
ゆえに、一社の企業だけが市場を独占しているような状況は、存続にとっては良くない状況なのかもしれません。
違いがある同業者が複数現れ、その業界が全体的に進化して行くことで、企業は存続が可能になるのかもしれません。
なお、その本によると、自然選択が働く前は、生物は、生まれては消えて行っていたのではないかと言うことでした。
確かに、研究者の場合も、ある研究分野(ある研究室)が消えてしまうのは、上の2つの条件が満たされなくなった時なのだと思います。
つまり、魅力的な研究者(または変わり者の研究者)がいなくなり、その研究分野に入って来る学生さんの数が少なくなった時が危ないのかもしれません。
また、その本によると、生物が存在し続けるためには、生物は増えなくてはいけないそうです。
確かに、YouTuberが増えなければ、YouTubeは存続しないのかもしれません。
また、確かに、人気のYouTuber(存続しているYouTuber)は、数多くの動画をアップし、その動画も同じ様な内容ではなく、少しずつ変異・進化していると思います。
5)環境の変化
その本によると、生物は、自然選択によって、多様化しつつ、環境の変化に合わせるように変化して行くそうです。
つまり、地球上の色々な環境(熱い、寒い、多湿、砂漠)に適応した結果として、生物は様々な種に多様化したとも言えるようです。
すると、生物と環境は一体化していると言える場合もあるのかもしれません。
環境が一定な惑星で生まれた生物は、同じ姿のままいつまでも生き続けて、もしかしたら複製を作らないかもしれないそうです。
一方、地球は自転軸が傾いているので、季節が生まれ、環境は一定にならないそうです。
人間は、環境(季節)の変化に対応するために、服を着たり、暖(だん)を取ったりしているので、人間には身体的な変化はほとんど起こらないのかもしれません。
(ちなみに、犬の場合は、ある季節になると毛が生え変わったりします。)
ただ、環境の変化は、人間の心には影響を及ぼしているような気がします。
長年会社に勤めていた方が、定年退職で、急に仕事を失うと、生きる気力を失ったかのような状態になってしまうと言う話はよく聞く話です。
当たり前の話になってしまいますが、状況や環境が変わると、人間の心は、時に激しく変化すると言うことだと思います。
逆に言えば、状況や環境が変わらなければ、人間の心は、激しく変化することはないと言うことかもしれません。(成長もないのかもしれませんが。)
しかし、山の奥に穏やかに住んでいる人でも、急に思い立って何かをしたくなることはあると思います。
つまり、状況や環境が変わらなくても、人間の心は、変わるのかもしれません。
この事は、生物学的にはどのように説明されるのでしょうか。生物学では取り扱わない問題かもしれませんが。
人間の心における変化は、激しい生存競争のなごりの様なものなのでしょうか。
確かに、心に全く変化がないと言う方はいらっしゃらないのかもしれません。
また、多くの場合、環境を変えれば、人間の心は、(次第に)変わるのかもしれません。
つまり、心を変えるには、普段は見たり聞いたり体験したりすることがないことをすれば良いのかもしれません。
エンターテインメントの本質は、環境変化による心の変化にあるのかもしれません。

6)生態系
生態系とは、生物とその周りの環境全てを含めたものを指すそうです。
そして、その生態系に多様な生物たちが棲(す)んでいれば居るだけ生態系は安定するそうです。
例えば、多様性が少ない生態系では、ある植物が気候の影響で枯れてしまうと、その植物を食べていた動物まで死んでしまうことになるそうです。
一方で、多様性が多い生態系では、ある植物が枯れてしまっても、代わりとなる植物が存在するため、枯れた植物を食べていた動物は助かることになるそうです。
また、一種が爆発的に増加することは、生物の多様性を低くするそうです。
つまり、その一種が生態系のバランスを壊し、その生態系の生物たちが絶滅することに繋(つな)がることもあるようです。
この生態系における生物多様性の話も、まさに企業や組織の話にそのまま当てはまる話だと思います。
やはり、企業や組織に似た様な人ばかりが集まってしまうと、良くないようです。
似た様な人ばかりが集まった組織では、意見は一致し易いようですが、多様な視点や考え方をもつことが必要とされる課題はあまり解決できないようです。
一方で、多様な考え方をもつ人々が集まった組織は、意見が一致しにくく議論に時間が取られるようですが、いかなる課題に対してもその解決力は非常に高いようです。

7)進化は進歩ではない
進化と言うと、より優れた生物、より万能な生物に進歩しているイメージがありますが、生物学的には、そのイメージは間違っているようです。
あらゆる環境や条件で優れた生物と言うものは、存在しないそうです。
生物は、自動的にただ環境に適応するように進化するのみで、進化に目的地はないそうです。
よって、生物の進化が、生物の進歩であるとは言えないそうです。
確かに、企業や組織も、あらゆる時代・あらゆる状況において、常に優れていると言うことはないのかもしれません。
逆に言えば、どんなに優れた企業や組織にも、必ず欠点や脆弱性(ぜいじゃくせい)が出て来てしまうと言うことだと思います。
8)生物システムと都市の類似性
電気信号は、生物の世界で広く使われている情報伝達の手段で、神経やその集合体である脳だけが使っている訳ではないそうです。
都市で言うと、電気信号はインターネット回線に対応するのかもしれません。
人間よりも遥(はる)か前に、生物のシステムは電気を利用していたと言うのは、考え深いです。
また、生物は、体内に血管を作って、その中に血液を入れて、心臓というポンプで、血液つまりは酸素や栄養などを体の奥まで届けているそうです。
都市で言うと、血管は水道管に対応するのかもしれません。
また、生物の消化器系の最後の方の部分は、都市で言うと、下水処理場やゴミ焼却場に対応するのかもしれません。

おまけ:人間の多様性
代謝とは、簡単に言うと、生物の体内での物質やエネルギーの流れのことでしたが、体外(環境)まで含めれば循環システムであると思います。
生態系は循環システムであると考えられています。
哲学(構造主義)の言うように、「存続するシステム」には、やはり「循環」という特徴があるようです。
そして、「存続するシステム」には、自己の存続を助ける恩恵や恵みがあるのだと思います。
例えば、社会には教育という恩恵があり、会社には給与や福利厚生という恩恵があります。
恩恵を受けるには、システムに従う必要があります。
既存のシステムに従いたくない場合は、自分でシステム(例えば会社)を作る必要があるのかもしれません。
ただ、自分でシステム(会社)を作ることは決して不可能ではないと思いますが、リスクが大きく普通は容易ではありません。
比較的容易にできることは、与えることかもしれません。
例えば、誰かにラーメンを作ってあげたり、DIYを手伝ってみたり、荷物をどこかに届けたり、情報を発信してみたり、子供たちの面倒を見たり、などです。
このような比較的容易なことがヒントやきっかけとなり、洗練されたり相手の欲しい物になったりすると、システム(店や会社)に繋がることもあるようです。
人間には多種多様なタイプがあると思いますが、次のようなタイプもいらっしゃるようです。
- システムに従い、その恩恵を享受することが得意なタイプ
- 自分の得意なことから、システムを作ってしまうタイプ
ちなみに、生態系の維持(保存)により積極的なのは、タイプ1なのかもしれません。
なぜなら、生態系は人間に恵みをもたらすシステムであるからです。
恵みだけとは限らないのかもしれませんが。







